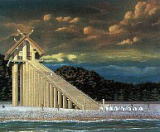|
 |
| 足立美術館の美しい庭園 |


白壁と堀割が続く
津和野・殿町通り |
「山陰の小京都」と呼ばれる城下町・津和野は土塀と鯉の町として最近ひときわ人気が出てきている。
格子戸や土塀が今も残る古い家並みの本町通りや、武士の屋敷が並んでいた殿町通りは往時の賑わいを偲ばせてくれる。
町中を流れる津和野川や通りの堀割には、沢山の鯉の群れが泳いでおり、町じゅう合わせると6万匹とも8万匹とも言われている。
津和野という名前の由来となったツワブキの鮮やかな黄色い花がいま、丁度満開を迎え、そこかしこで咲いている。

津和野ゆかりのツワブキ |
松江についたのは夕方。小雨の中に霞む宍道湖、ライトでボーッと浮か び上がっている夕暮れの松江城がなんとも幻想的である。そこで一句。 び上がっている夕暮れの松江城がなんとも幻想的である。そこで一句。
「うす墨で 画きたるごとき 宍道のうみ」
「霧雨に けむる宍道湖 秋深く」
ホテルでは、観光客に「どじょうすくい」を踊って見せてくれる。
宍道湖といえばシジミが有名であるが、今は資源保護のため、シジミを採ってもよい曜日、時間帯がきめられているそうである。
「蜆採る 船点々と うみの朝」 |
二日目は、出雲大社へ参拝する。10月は「神無月」と呼ぶが、ここ出雲の方では、全国の神様がこの地に集まってくるため「神在月」(カミアリヅキ)と呼んでいる。
縁結びの神、福の神として全国的に親しまれている出雲大社。
長さ8m、重さ1,500kgの大しめ縄が参拝者の目をひいている。 |
 |

重さ1,500kgの大しめ縄 |
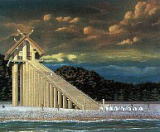
古代出雲大社の想像図 |
最近、平安後期の本殿を支えていた巨大な柱が発掘され、空中高くに建造されていたであろう本殿の姿に、古代のロマンをかきたてられる。 |

指月山 |
この夜は、山口県・萩の指月山(シヅキヤマ)の麓に泊る。
ここは、1604年、毛利輝元が築いた萩城の跡で、現在は堀や城壁の一部、石垣が残るのみで、指月公園として整備されている。 |
三日目、天気は完全に回復し、先ず、吉田松蔭をまつる松蔭神社を参拝する。
境内の中にある「松下村塾」の建物や、安政の大獄前に幽閉されていた幽囚室のあまりにも小さいのに驚かされる。
猫が一匹、人見知りもせず、悠然と座って参拝客を迎えている姿がなんとも可笑しい。
猫の出迎え
 |
|

松下村塾

松蔭神社 |
かって、吉川氏6万石の城下町であった岩国。城山にそびえる岩国城、澄んだ錦川、その川にかかる日本三名橋の一つである錦帯橋、まさに名画を見る思いである。
この12月から3年間、50年に一度の架け替え工事が始まり、しばらくは美しい姿が見れなくなるのは淋しいことである。
橋を渡りきると、藩主吉川氏の館跡があったところに吉香公園がある。紅葉や四季折々の花が咲き乱れている。

吉香公園 |
 
錦帯橋 |
 

秋の「安芸の宮島」

能舞台 |
日本三景の一つである宮島は、古来より神の島としてあがめられてきた。世界文化遺産にも登録されている厳島神社は、宮島のシンボルである。フェリーボートでわたると、緑の原生林、青い海と空のなかにひときわ目立つ朱塗りの鳥居と建物が目に飛び込んでくる。
6世紀後半に創建された古い神社を、平清盛が1168年、今の姿に立て替えたもので、本殿、能舞台など各社殿が回廊で結ばれている荘厳雄大なつくりである。
隣接する五重塔や秀吉を祭ってある千畳閣も威容を誇っており、そこから眺める海は絶景である。

五重塔
|

千畳閣 |
|

放し飼いの鹿 |
島には、何百頭の鹿が放し飼いされており、観光客に餌をねだるのか、すり寄ってくるのは可愛い反面、気をつけないと、みやげ物を入れた紙袋を食べられてしまう。 |
|
|






 び上がっている夕暮れの松江城がなんとも幻想的である。そこで一句。
び上がっている夕暮れの松江城がなんとも幻想的である。そこで一句。