
2017.10.29から2泊3日で福島県の会津地方へ紅葉を見に行った。
【1日目】
JR多治見駅⇒JR塩尻駅⇒鶴ヶ城⇒猪苗代温泉
【2日目】
あだたら山ロープウェイ⇒ゴンドラ山麓駅<磐梯吾妻スカイライン>浄土平<磐梯吾妻スカイライン>中津川渓谷)<磐梯吾妻レイクライン>
裏磐梯五色沼⇒裏磐梯猫魔温泉<泊>
【3日目】
会津鉄道もみじ列車乗車⇒塔のへつり⇒大内宿⇒JR塩尻駅⇒JR多治見駅
の予定であったが、2日目に積雪のため安達太良山周辺の各道路で通行止めがあり、浄土平と、中津川渓谷には行けなくなった。

会津若松でまず最初に鶴ヶ城に向かった。
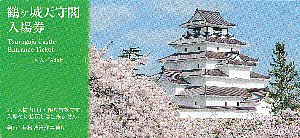 一般に鶴ヶ城(つるがじょう)と言うが、福井県敦賀市にあった敦賀城(つるがじょう)との混同を避けるため、会津若松城と呼ばれることが多い。また、旧称である黒川城、または単に会津城と呼ばれることもある。
一般に鶴ヶ城(つるがじょう)と言うが、福井県敦賀市にあった敦賀城(つるがじょう)との混同を避けるため、会津若松城と呼ばれることが多い。また、旧称である黒川城、または単に会津城と呼ばれることもある。数多くの戦国大名が治め、幕末の戊辰戦争でも有名なこの城は、明治7年に取り壊されたが、昭和40年に5層の天守閣に復元された。平成13年には南走長屋と干飯櫓が復元、平成23年には赤瓦葺替修繕工事が完了し、幕末の鶴ヶ城の姿に生まれ変わった。
天守閣内は博物館として公開されており、また 城を中心に広がる3、720平方mの公園は春の桜、秋の紅葉で人気の高い観光スポットとなっている。


鶴ヶ城天守からの眺望
鶴ヶ城から今夜の宿泊地猪苗代へ向かう。

ホテルから猪苗代を望む

ホテルの裏からの眺め
二日目、昨日から山では雪との情報があり、心配しながらも安達太良山(あだたらやま)へ向かう。昨日は運休したロープウェイが今日は営業をしていた。
高村光太郎の「智恵子抄」で知られる安達太良山は福島県中部にある活火山である。日本百名山、新日本百名山、花の百名山などに選定されている。磐梯朝日国立公園に指定されており、ガンコウラン(岩高蘭)、クロマメノキ(黒豆の木)などの高山植物が保護されている。
山頂からは、沼ノ平周辺の荒涼とした火山の景観がみどころとのことだったが、ロープウェイを降りたところから、積雪のため足元が滑り行けなかった。


この後、浄土平と、中津川渓谷へ行く予定であったが、安達太良山周辺の各道路で通行止めがあり行けなくなっていたので、安達太良山高原を走った後、本場の喜多方ラーメンを食べに喜多方市へ行った。

安達太良山高原
喜多方ラーメンを食べ、喜多方市を散策してから、裏磐梯五色沼へ向かう。
全長約4.5kmの自然探勝路に沿って、柳沼、青沼、瑠璃沼、弁天沼、竜沼、みどろ沼、赤沼、毘沙門沼など磐梯山の噴火によってできた湖沼群が点在する。
水の色が湖沼によって、緑、赤、青などの様々な色彩を見せることから、五色沼と呼ばれている。五色沼の水の色は、水中の酸化鉄やアルミニューム、珪酸など微粒子の大きさにより、赤色になったり青白色になったりするという。
一帯は国立公園の特別保護区に指定されている。
柳沼
柳沼
青沼

青沼

青沼
瑠璃沼
毘沙門沼
毘沙門沼

毘沙門沼


毘沙門沼
今夜の宿泊は、五色沼すぐそばのレイクリゾートホテル。
翌朝、ホテルの庭に出ると、磐梯山が綺麗に見えた。
レイクリゾートから見た磐梯山

朝食後「会津鉄道もみじ列車」に乗って沿線の紅葉を楽しみに行く。
猫の駅長がいることで評判となっている「芦ノ牧温泉駅」からトロッコ列車に乗る。
走行中ほとんどの時間を南会津町、下郷町の紅葉に囲まれた大自然を見せてくれる。
特に景観の良いポイントでは一旦停止してくれる。
猫の駅長の「芦ノ牧温泉駅」 |
 会津鉄道乗車券 |
「会津鉄道もみじ列車」 |

茅葺屋根の駅舎のある「湯野上温泉駅」。
この駅で、上下線のすれ違いのため、一旦停車。しばし写真撮影。

「塔のへつり駅」

塔のへつりは、福島県会津地方を流れる大川が形成する渓谷で、大川羽鳥県立自然公園の一角を占める。
1943年(昭和18年)国の天然記念物に指定されている。一帯は岩が長年の歳月により侵食、風化されてできた柱状の断崖である。
全長200mにわたって、大規模な奇岩が並んでいる。主なものには屏風岩、烏帽子岩、護摩塔岩、九輪塔岩、櫓塔岩、獅子塔岩、鷲塔岩などがあり、これらの岩を巡るように通路が彫られているが、経年による崩落等のため、吊橋を渡している舞台岩周辺以外は立ち入り禁止となっている。
「へつり」とは会津方言で、川に迫った険しい断崖のことである。なお、「へつり」は「岪」(山冠に弗)という漢字表記があるが、現在使われないため、かな表記が標準化している。




この後、江戸時代の町並みを今に残す宿場町「大内宿」に向かう。
下野街道と呼ばれた会津と日光を結ぶ街道には、参勤交代の大名行列や旅人、行商人などの宿駅として重要な役割を果たしていた「大内宿」があり、茅葺き屋根の民家が並んでいる。
明治時代になると国道121号線が開通し、この宿場町はすたれてしまったが、戦後さまざまな人の尽力によって貴重な文化財として保存されるようになった。
現在は、約400mの長さで道の両側に30軒以上の茅葺き屋根の古民家が軒を連ね、飲食、土産物屋、民宿などさまざまなお店が営業していおり、国の重要伝統的建造物郡保存地区にも指定されている。

一本の太い長葱を箸代わりにして
食べる名物の「一本ねぎ蕎麦」
いろいろな手作りの民芸品が店先に置かれている。