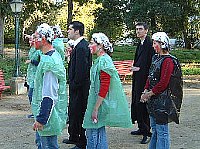情熱のスペイン・悠久のポルトガル |
11月4日からスペイン、ポルトガルの旅に出かけた。
成田空港から飛行機でオランダ・アムステルダムへ飛び、そこでEUへの入国手続きを済ませ、あとは国内線扱いでスペインのバルセロナまで飛ぶ。バルセロナからは全て観光バスで移動し、ポルトガルのリスボンまで合計2830km、8日間にわたる長い旅となった。
寒波がきているため、防寒対策を万全にということであったが、連日晴天に恵まれ、逆に汗ばむほどであった。
帰りは、リスボンからドイツ・フランクフルト経由で成田へ戻ってきた。 |
|
 |
左の地図上の地名をクリックするとそこの記事にジャンプします。 |
|
【バルセロナ】
 |
| カサ・ミラ |
人口200万人を超えるスペイン第二の大都会バルセロナは、ピカソやミロなど数多くの芸術家を育んだ芸術の街である。
19世紀末の芸術運動(モデルニスモ)を代表する天才芸術家ガウディの作品が数多く見られる。
色とりどりのタイルでモザイク模様をつけたカサ・バトリヨ、アブストラクト風の曲線を多用した外観のカサ・ミラ、100年近く造りつづけられているサグラダ・ファミリア(聖家族教会)、世界遺産にもなっているグエル公園などがその代表的なものである。 |
 |
今だに建築中の
サグラダ・ファミリア |
サグラダ・ファミリア(聖家族教会)
1882年フランシスコ・デ・ビヤールが建築に着手し、1891年ガウディに引き継がれたが、ガウディの没後80年以上経ってもまだ建築が続いている。12本の塔を持った壮大な建物全てが完成するのは、100年後とも200年後ともいわれるが、現地ガイドの話しでは、ガウディ没後100周年を記念して、2020年代後半には完成したいそうである。建物を覆うようにして埋め尽くされる石造の彫刻には現在、日本人彫刻家・外尾悦郎氏が携わっている。
|
 |
| グエル公園 |
世界遺産 グエル公園
モザイク模様のタイルのベンチが野外劇場を囲み、極彩色の動植物のオブジェが目を引く。もともとはガウディの一番の理解者である経済人エウセビオ・グエルが、60軒規模の田園都市を作る目的でガウディに造らせたものであるが、市街から遠いという理由で人々に受け入れられなかったため、公園として開放されるようになった。予定60軒に対して、実際に建築されたのは2軒で、そのうちの1軒にガウディが住んだという。その家は、今はガウディ博物館となっている。 |
|
 |
 |
| 知事候補者の選挙看板 |
丁度今、ここカタルニア地方の知事選挙の期間中で、町角の電柱には候補者の看板で埋め尽くされていた。中にはダンボール箱のたて看板もあった。そういえば、今は日本でも総選挙の真っ最中、不在者投票はちゃんと済ませてきたが、自民党が勝つか民主党が勝つか気になる。 |
|
【バレンシア】
バルセロナから地中海を左に眺め南下すること約350km、トイレ休憩をはさんで5時間、100万人都市のバレンシアにつく。「火祭り(ファージャ)で知られるバレンシアは農作物の栽培が盛んで、スペインの名物料理パエリヤは、ここの豊かな食材を元にして生まれたと言われている。
 |
| 闘牛場 |
町なかには、闘牛場、アールヌーボー様式の鉄道駅、13世紀頃の遺跡など歴史を感じさせるものが豊富にある。中でも、13世紀中ごろ建設のカテドラル(大聖堂)、世界遺産ラ・ロンハが代表的なものである。
カテドラル(大寺院)
13世紀中ごろから14世紀末にかけてイスラム教のモスク跡に建てられた。17〜18世紀に改修されたため、バロック様式やネオ・クラシック様式が見られる。すぐそばには、バレンシアのシンボルとも言えるミゲレテの塔がそびえている。
世界遺産 ラ・ロンハ
15世紀に建てられたスペインを代表するゴシック様式の建物で、絹の交易所として使われていた。現在は各種イベント会場として開放されている。 |
|
【クエンカ】
バレンシアから延々と続く山あいのオレンジ畑を抜けていくと、奇岩がぼこぼことそそり立つクエンカの町につく。
奇岩に囲まれ、山の斜面に築かれた城塞都市クエンカは、「魔法にかけられた街」と呼ばれるぐらい、幻想的で不思議な雰囲気を漂わせている。世界遺産に登録されている。
 |
 |
| 延々と続くオレンジ畑 |
奇岩がぼこぼこ |
|
カサ・コルカーダ(宙吊りの家)
切り立った崖の上に家々が建ち並び、今にも崩れ落ちそうに見える不思議な景観である。 |
|
 |
【マドリッド】
イベリア半島の中央に位置するスペインの首都マドリッド。街の起源は、9世紀にアラブ人が砦を築いたのが始まりと言われている。1561年、フェリペ2世がトレドからマドリッドへ遷都して以来、スペインの都市として飛躍的な発展を遂げ,現在の政治、経済の中心地となっている。
市内には広大な公園や、広場が豊富にあり市民が憩っている。また、国内最大の目抜き通りグランビア通りは、大勢の人出で賑わっている。
マドリッド王宮
1738年から1764年にかけて建設された140m四方の壮麗な宮殿で王宮内の部屋数は2800にのぼる。
ここに来た日に丁度、スペイン皇太子の婚約発表があり、TVではその報道でもちきっていた。
 |
| プラド美術館 |
プラド美術館
フランスのルーブル美術館、ロシアのエルミタージュ美術館と並ぶ3大美術館の一つで、1785年から1808年にかけて建設された。収集美術品は8000点以上を誇り、ゴヤ、ベラスケスら17〜18世紀に活躍したスペイン絵画の巨匠らの絵が、初期から晩年まで、その画風の変遷までわかるようになっているのはさすがのものと言える。
中でも、ゴヤの「着衣のマハ」と「裸のマハ」は昔、教科書でしか見たことがなかったので、現物を目の前にして感動的であった。
|
 |
| 闘牛士らと記念写真 |
闘牛ショー
郊外で夕食後、闘牛ショーを見る。闘牛を鮮やかに操るマタドールのマント捌きに感心する。
|
|
【トレド】
 |
| 城塞都市トレド |
マドリッドの南70km、三方をタホ川に囲まれた小高い丘の上に立つ城塞都市トレドは、「スペインで一日時間があれば、迷わずトレドへ行きなさい」と言われるほど美しく、6世から16世紀に半ばまで、スペインの首都として栄えた歴史を物語る遺跡が多く見られ、中世の街並みは世界遺産に登録されている。
スペイン絵画の巨匠エル・グレコはトレドの魅力に惹かれ、この街に移り住んで活躍した。14世紀に建造されたサント・トメ教会に入ったところに飾られている「オルガス伯の埋葬」は彼の大傑作の一つである。
カテドラル(大聖堂)
1493年に完成したスペインカトリックの総本山で、高さ90mの鐘楼が壮観
|
|
【ラ・マンチャ】
 |
| 白い巨人群 |
高速道路に乗って一路ラ・マンチャ地方へ向かう。道の両側にはオリーブやブドウの畑が広がっている。時々真っ黒の牛の看板に出会う。シェリー酒(ワイン)で有名なオズボーン社の看板であるが、一切文字が入っていない。見ればわかるというものか。それにしても、スペインの高速道路は一般車にとって快適に走れる。無料にもかかわらず、もともと日本と違って、車の密度が小さい上に、トラックは100km以上出せないように作ってあるし、低速ラインしか走ってはいけない、また、休みの日にはトラックは高速道路を通ってはいけないという決まりがあるそうである。
やがて、風車の町、コンセグラに入る。セルバンテスの小説「ドン・キホーテ」の舞台として知られ、16世紀に造られた白い風車群が、巨人と間違えて格闘したドン・キホーテの姿を思い浮かばせてくれる。 |
|
【コルドバ】
| アラビア語で「大きな川」という意味のグアダルキビル川に沿って開けた町コルドバは、8世紀から10世紀にかけてヨーロッパの学問、芸術の中心地として繁栄し、ヨーロッパでも最大級の都市に成長した。10世紀には、イスラム教王国の首都となり、「西方の真珠」と呼ばれるようになった。 |
 |
| メスキータ |
世界遺産 メスキータ
コルドバの中心に立つイスラム教王国の栄華を象徴するモスクである。8世紀半ばに建造されたもので、イスラム寺院としては、メッカのカーバ寺院に次ぐ第2の規模である。何度も増改築を繰り返している間にイスラム教とキリスト教とが渾然一体となった珍しい教会となった。メノウ、大理石、花崗岩でできた850本もの赤と白のアーチが林立しており、スペインで一番素晴らしい聖堂とも言われている。 |
 |
| 花の小径 |
花の小径
僅か50mほどの狭くて短い小径であるが、両側の民家の窓にはびっしりとフラワーポットがとり付けられてある。花のシーズンには、白い壁と対照的に色とりどりの花で飾られることであろう。ただ、今はシーズン外のため「花の小径」ならぬ「葉っぱの小径」となっている。然しながら、これぐらいの規模の小径で、なぜ観光スポットになっているのかはよく分からない。
|
 |
| 向こうの山にもオリーブ |
バエナの町
次の目的地グラナダへ向かう途中にオリーブの一大生産地バエナを通る。山また山、全山オリ−ブ畑である。さすがスペインは世界一のオリーブ生産量を誇るだけのことがある。オリーブの実の収穫は人力だと聞いて気が遠くなる。値段も高いはずである。
日本では今丁度紅葉のシーズンであるが、スペインでは真っ赤に燃える紅葉は滅多に見られない。樹の種類が違うのか、気候のせいか、黄色と茶色に変わった樹しか見られない。あとはオリ−ブや松、杉のような常緑樹が殆どである。
|
|
【グラナダ】
 |
| フラメンコ・ショー |
グラナダへ着いて遅い夕食の後、アルハンブラ宮殿を見下ろす小高い丘の上の古びた店でフラメンコ・ショーを見る。
30人も入れば満員となる小さな部屋で、すぐ目の前で踊る伝統的なフラメンコの激しいステップと情熱的な踊りに魅了される。
|
 |
| アルハンブラ宮殿 |
世界遺産 アルハンブラ宮殿
14世紀に建造された中世イスラムの傑作アルハンブラ宮殿は、シェラネバダ山脈を背にした美しい宮殿で、コーランに描かれた天上の楽園を再現し、アラビア芸術の最高傑作と言われる。「ライオンのパティオ(中庭)」は12頭の獅子に支えられた噴水がシンボルとなっている。
石壁が赤鉄を含んでいることからアルハンブラ(赤い城)と呼ばれた。
哀愁のあるギターの名曲「アルハンブラの想い出」が、どこからか聞こえてきそうである。
|
ヘネラリーフェ庭園
14世紀初め、グラナダの太守が夏の別荘として建造したもので、綺麗に刈り込まれた杉に囲まれた通路、色とりどりの花に息吹を与えている噴水や清流が涼気を誘う。 |
|
【ミハス】
 |
| サン・セバスチャン通りで |
グラナダから地中海に沿ってミハスへ向かう。国際リゾート地として知られるコスタ・デル・ソル(太陽海岸)を左に見て、海岸線から10kmほど内陸部に入ると、「アンダルシアのエッセンス」と呼ばれる白壁の映える小さな村ミハスが見えてくる。山の斜面に沿って立ち並ぶ白い家、四季折々の花で飾られる白壁、情緒あふれる坂道など昔ながらの素朴な雰囲気が感じられる。
アンダルシアで一番美しいと言われるサン・セバスチャン通りは、数々の映画撮影に使われたと言う。かっては、ロバート・レッドフォードもここに住んでいたそうだ。
展望台に行けば、ジブラルタル海峡が目の前に見える。天気の良い日には、アフリカ大陸も見えるそうであるが、残念ながら今日は雲に隠れていた。
スペインでただ一箇所という四角い闘牛場もある。陽光を照り返す白い街中のオープンテラスで飲食する人、ロバのタクシーで観光する人、土産物屋で品選びしている人、皆の顔が底抜けに明るい。
|
 |
| スペイン料理パエリア |
昼食でスペインの代表的な料理、エビ、鳥肉、ムール貝の入ったパエリアを食べる。大鍋で作ったパエリアをシェフが手際よく小皿に分けていく。
久し振りに残さず食べた。
|
 |
【セビリア】
オペラの名作「カルメン」、「セビリアの理髪師」、「フィガろの結婚」、「ドン・ジョバンニ」などの舞台としてあまりにも有名なセビリアは、ヨーロッパとイスラムの文化が見事に調和し、「アンダルシアの華」とも称される。
コルドバから続いているグアダルキビル川沿いに建つている海の見張り役・黄金の塔、セビリア万博のときに造られた広大なスペイン広場など観光名所がたくさんある。市内の街路樹として4万本ものオリ−ブが植えられており、オリーブの実がたわわに実っている。取って食べてよいものかどうか迷ってしまう。
アラビア文化を伝えるアルカーサル(城塞)、世界の三大寺院に入るカテドラルは世界遺産に登録されている。
 |
 |
 |
| 広大なスペイン広場 |
4万本ものオリ−ブの街路樹 |
黄金の塔 |
カテドラル(大寺院)
イスラム勢力を駆逐したことを示威するため、「後世の人が呆れるほど大きな教会を造ろう」と、イスラム寺院跡に15世紀はじめから1世紀をかけて造られたゴシック様式の大寺院で、間口116m、奥行き76mもあり、バチカンのサン・ピエトロ寺院、ロンドンのセントポール寺院に次ぐ大きさである。街のシンボルとなっている高さ98mの鐘楼ヒラルダ(風見)の塔は、12世紀にイスラムのミナレット(尖塔)として建てられたもので、1764年以来、時刻を打ち続けている。我々が行ったときに、ちょうど午前10時の鐘が鳴り響いた。
セビリアの街をあとにして、ポルトガル・エヴォラ地区へ向かう。セビリア郊外の車窓には今までとは一転した風景が広がって来る。樫の木の林である。ここで放し飼いされて樫の実を食べて育った黒豚で作った生ハムは、「イベリコ・ベリョータ」といわれ最高級品だそうである。
ポルトガルとの国境の町をとおるが、スペイン側、ポルトガル側ともに、昔の入国管理事務所だった小さな建物が僅かに残っているだけで、言われなければ気が付かずに通り過ぎてしまいそうである。 |
|
【エヴォラ】
バスに乗ったまま、何の手続きもなくスペインからポルトガルへと入る。さすがにEUとなってからは便利なものである。車窓にはブドウ畑、綿花畑、オレンジ畑、オリ−ブ畑がめまぐるしく飛び込んでくる。幹の皮がはがされた樫の木も並んでいる。コルクの材料となるコルク樫である。
世界遺産 エヴォラ歴史地区
市民の憩いの場となっているジラルド広場には屋台も出て沢山の人で賑わっている。たまたま訪れた日は「栗を食べる日」とかで、焼き栗を売っている屋台が繁盛していた。この広場を中心として、古代ローマが築いた建物が多く残っている。その代表的なものが、2〜3世紀にローマ人によって建てられた14本のコリント様式の柱が立つディアナ神殿の跡である。
 |
 |
| ジラルド広場 |
焼き栗の屋台 |
|
|
 |
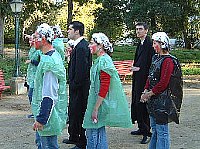 |
| 大学の新入生歓迎行事 |
近くの公園で、若者たちが頭をシャボンだらけにして走り回っているのを見かけた。大学の新入生に対する上級生の歓迎行事だそうである。日本では、いじめで問題になるかも。 |
|
【リスボン】
 |
 |
| 哀愁のファド・ディナショー |
リスボンに到着後、リスボンで生まれた、ポルトガルの代表的な音楽ファドが聞けるディナー・ショーに行く。ファドと言えば、1960年代にアマリア・ロドリゲスが歌った「暗いはしけ」が思い出される。彼女は二,三年前に亡くなったそうである。ギターとポルトガルギター(ビオラ)の伴奏で、切々と歌うファドに哀愁を感ずる。
|
ヨーロッパ大陸最西端に位置するポルトガルの首都リスボンは人口100万人を超える大都市である。大航海時代に世界の玄関口として栄華を極めた名残を今にとどめている。
 |
| ベレンの塔 |
 |
| ジェロニモス修道院 |
世界遺産 ベレンの塔
リスボン港を守る要塞として、船舶監視のため1519年に建てられたマヌエル様式の5階建ての建物。その優美な姿から「テージョ川の貴婦人」と呼ばれたが、その名前とは裏腹に、1階は水牢、2階は砲台、3階が王族の居室として使われた。
発見のモニュメント
バスコ・ダ・ガマがインド航路を発見し、マゼランが世界就航を果たし、世界の海に君臨したポルトガル。バスコ・ダ・ガマがインドへ旅立った船出の地に、帆船をかたどった高さ53mの記念碑が建っている。1960年に建造され、帆船に乗った人々の姿をモチーフにした像は、海洋国家ポルトガルのシンボルとなっている。
世界遺産 ジェロニモス修道院
テージョ川に面して建つ壮麗なゴシック風の白亜の大建築。16世紀、エンリケ航海王子とバスコ・ダ・ガマの偉業を称えるために、海外遠征で得た巨万の富で建てられた。中庭を囲む回廊がゴシック風で美しい。
|
 |
 |
| ユダヤ人街 |
リスボン市内にある昔ながらのユダヤ人街を歩く。狭い入り組んだ路地、窓々に干した洗濯物、地べたに野菜や日用品を並べて売っている老婆、薄汚れた食べ物屋などいかにも生活感に溢れた街である。ここの一角で昼食をとり、次の目的地シントラへ向かう。 |
|
 |
| シントラ王宮 |
シントラ地区
リスボンからほんの2,30分で行ける郊外にイギリスの詩人バイロンが「地上のエデン」と称えた美しい街シントラや、ユーラシア大陸最西端のロカ岬がある。
世界遺産 シントラ王宮
14世紀末の建物で、1910年の共和制宣言まで、歴代国王の夏の離宮としてて使われていた。中にそびえている二つのとんがり帽子の形をした煙突は、調理場の排気ダクトで、ワイングラスの形を模して作らせたものだそうだ。
|
 |
| 西の果てロカ岬 |
ロカ岬
ユーラシア大陸最西端の岬で、大西洋に落ち込む高さ140mの断崖の上に瀟洒な灯台と記念碑が建っている。その記念碑には、ポルトガルの国民的詩人ルイス・カモンイスの「ここに地果て、海始まる」の言葉が記されている。
|
 |
| 華やかな地下鉄駅 |
最後の朝、時間があったのでリスボンの町のなかを歩いてみる。地下鉄駅構内は、サイケ調のモザイク模様で華やかなのにはびっくり。100円ほどでどこまでも行けるというので二度びっくり。
結構いろんな花が植えられ、美しく咲いているのを見かけるが、これもお国柄なのか。
ホテルのそばでスーパーを見つけ、お土産を買い込む。ツアーのガイドが連れて行ってくれる土産物屋よりはるかに安いものがそろっているのでありがたい。 |
|